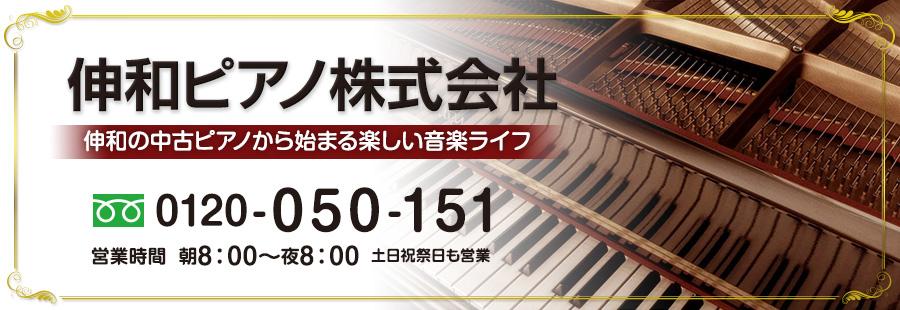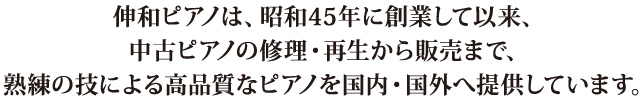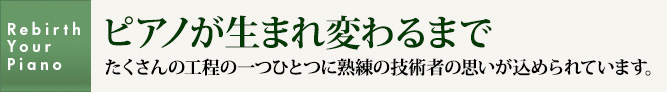中古ピアノの修理再生
ピアノ工房(約600坪)で新品同様な仕上げから、一般的な仕上げまで、お客様のご注文に合わせて修理再生を行っています。
中古ピアノの販売
国内は、楽器店・調律師・一般のお客様などに販売しています。海外は、北アメリカ・ヨーロッパ・オーストラリア・アジア等の各地域に輸出しています。
中古ピアノの運搬業務
ピアノ専門運送を行っています。
お引っ越しに伴うピアノのご移動や、ご不要となりましたピアノの引取り・買受けを承っております。
入荷検査

入荷したピアノは、経過年数による経年変化や使用頻度などにより、保存状態が大きく異なります。そのため入荷時点で、ピアノの状態を部品ごとに詳細に記録して、ピアノを再生する際の部品交換や塗装作業などの資料として保存いたします。
保管

入荷検査が完了したピアノは、ピアノ専用倉庫(約7260㎡=2200坪)に保管します。中古ピアノの在庫は常時3000台前後あります。その後、お客さまからのご注文に応じて保管倉庫からピアノ工房に運ばれ、それぞれの整備作業に入ります。
クリーニング

ピアノ工房に運ばれたピアノは分解された後、お客さまのご要望に応じて、それぞれ専用の作業ブース(大小13ブースあります)に移動し、様々な作業に取りかかります。上の写真は、基本的な清掃や研磨作業の様子です。
塗装修理

塗装修理が必要なピアノは、専用の塗装ブースで塗装が施されます。塗装ブースは3基あり、フル稼働した場合は全塗装も含めて1ヶ月に150台前後のピアノを新品同様に仕上げることができます。塗装作業は、下塗りをして、乾燥させて、研磨をし、さらに塗装して、乾燥させて、研磨して…という作業を何度も繰り返して徐々に完成させていきます。
乾燥室での保管

塗装作業が完了したピアノは専用の乾燥室に移動させます。この乾燥室は、1年中(24時間365日)温度と湿度を一定に保つよう管理されており、塗装完了後約1週間寝かせます。これにより水分を蒸発させ、塗装した部分を安定させることができます。乾燥後に研磨して仕上げられたピアノは、さらに1週間程度寝かせて、再仕上げを行います。
ラッカー塗装の仕上げ

乾燥工程が完了したピアノは、塗装を施した部分の研磨作業に入ります。この作業は、全体を鏡の面のように、傷がまったく無い“ピカピカ”の状態に仕上げるための作業です。塗装面の塗料はひび割れを防ぐために厚塗りはしておりません。そのため、この作業を早く正確に行えるようになるまでには、個人差がありますが、2~3年以上の経験が必要となります。
傷の修理・ポリエステル塗装

ポリエステルの塗料で塗装されているピアノの場合は、傷の修理もポリエステルの塗料で行います。ポリエステルの塗料は、短時間(2時間程度)で非常に硬く固まるため、部分的な修復を繰り返します。当社の修復基準は、どこを修復したのかがまったく判断できないように仕上げていく技術を求めています。この修復作業で一人前になるためには、数年の経験を積む必要があります。
内部部品交換室での作業

この部屋では、ピアノの内部に使用されている各種部品の交換や調整作業などを行っています。とても大切な作業であり、1ミリメートル以内の調整が必要な部品がほとんどです。また、同じ作業の繰り返しが多いため、繊細な作業を根気よく続けられることが得意な女性向きの仕事です。この作業は、主に女性が担当しております。
バッドスプリングコードの交換

バットスプリングコードという部品は、同じ鍵盤を1秒間に5回・6回と、それ以上に早く弾くことができるようにするための装置です。例えばトレモロのような早い打弦は、ピアノのハンマーを瞬時に元の位置に戻すことが必要ですが、それを可能にするための部品です。この部品は経年変化などにより、素材が劣化して切れてしまう場合があります。そろそろ切れそうな場合も含めて、新品の素材に張り直します。
鍵盤のブッシングクロス交換

鍵盤の上下運動の時に、鍵盤を支えている2本のピンとの間に摩擦が生じます。この摩擦を防ぐために羊毛素材(ブッシングクロス)を使用して、ピアノの木と鉄のピンが直接当たらないようにすることができます。摩擦による摩耗、または虫などの被害状況によって、減ったり消失してしまうことあります。そのため、新しいクロスの張り替えが必要になります。当社では、カシミヤ混紡の高級素材を使用しています。
鍵盤の張り替え

ピアノの鍵盤は使用していくうちに剥がれたり、欠けてしまったり、変色したりとさまざまな状態に変わっていく場合もあります。そのような場合、新しい鍵盤に張り替えることが必要です。この写真はその作業を行っているところです。
鍵盤の調整1

ブッシングクロスを交換するほどの消耗がない場合は調整によって摩擦を軽減します。写真はその作業を行っているところです。クロス類の素材は羊毛です。湿気を含んで膨張したりすることがあります。そのような状態になると、摩擦が多くなって鍵盤の上下運動に支障をきたしてしまいます。極端な場合には、全く動かくなる時もあります。
鍵盤の調整2

この写真は、鍵盤を押し込んだ状態で、深さを一般的な規定通りに調整することと、鍵盤の上面の高さを一定に保つために調整する作業を行っています。深さが一定していない場合や、鍵盤の上面が凹凸の状態だと、見た目も良くありませんし、また、演奏にも大きく影響を及ぼします。演奏する人に弾きやすさを感じていただくためにも、この作業は不可欠なものです。
オーバーホール作業1

先程の4番目の写真に、グランドピアノの響板の塗装作業がありました。塗装作業の前にピアノ線を外してフレーム(鉄骨)を降ろしますが、この写真はちょうどピアノ線を外している場面になります。ピアノ線は全体で約230本あり、その総張力は約20トンになります。ピアノ線を外す時は、全体的に少しずつバランス良く張力を緩めていきながら、取り外していきます。
オーバーホール作業2

この写真は、グランドピアノのアクションに新しいハンマーを取り付けている作業の様子です。各セクションごとに両端のハンマーが付いていますが、それを基準にして間のハンマーを取り付けていきます。ハンマーを取り付けた後、しっかりとした音を出すためには、まだまだ多くの作業が必要となります。完成するまでには、さらに数十時間を費やさなければなりません。
整調・整音作業

整調・整音はオーバーホールの最終段階での作業となります。この作業は非常に高度な技術を必要としますので、相当な経験を積んだ調律師でないと、良い音に仕上げることはできません。当社では調律師の育成のため、年間を通してプロのピアニストを招いて研修会を行っています。当社の調律師の中から3人を選んで、それぞれの調律師が仕上げたピアノ3台を使用して社内演奏会を行い、プロのピアニストから多くのアドバイスをいただき、そのアドバイスを参考にして、技術の向上に役立てております。
調律作業

この写真は、調律専用室での作業風景です(写真撮影のためにドアは開けてあります)。調律師の仕事は、一般的な「調律」と呼ばれるものの他に、左の説明の「整調」「整音」を加えた三種類となります。この三種類の仕事をすべて行わないと、より良い状態にはなりません。それらの作業にかかる時間は、状態によりまして、2時間から8時間以上かかる場合もあります。グランドピアノの場合は10時間・20時間・30時間とピアノの状態によって所要時間は大きく異なります。
完成検査

それぞれの工程ごとに完了検査がありますが、ここでの完成検査とは、全体の作業が終了し組立が終わった状況で行われるもので、細部に渡って入念に調べられます。少しでも問題が見つかった場合、元の部門に戻され再仕上げの指示が出されます。そして、その再仕上げが終わると再度検査を受けることになります。検査を通過したピアノは、その時点では99.99%完璧な商品に仕上がっています。その結果、出荷後のクレームはほとんど発生していません。