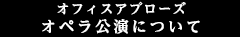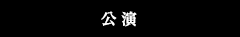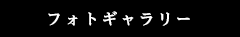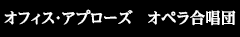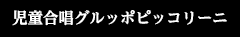砂川稔――音楽と共に六十年 山崎裕視
何でもないような偶然が、時として人の一生を決定づけることがある。十五歳の砂川稔少年の場合もそうだったに違いない。
戦争末期には塹壕掘りに明け暮れた彼だが、終戦と共に再び実家のあった大阪に戻り、焼け跡のバラック校舎で旧制中学校の授業を受けていた。ある日の放課後、級友のひとりがアコーディオンを教室に持ち込み、弾きはじめた。戦火を耐えたその楽器から流れ出た音楽は、軍歌しか知らなかった彼の心に、洗うような感動を与えた。「音楽とは良いものだ」とつくづく思った。茫然と聴き入っているうちに、外が暗くなっているのにも気づかなかった。ブーちゃんという綽名の級友の、「音楽学校ちゅうもんがあるんやぞ」と告げた一言が脳裏に刻み込まれた。
中学卒業後、一時は東京と神戸の神学校に籍を置いた。しかし、彼の心の中では、音楽への憧憬が日ごとにふくらんでいき、教学への精進とのはざまで稔は悩み抜いた。意を決して父に、「音楽学校に入りたい」と告白した時、思いがけずも父はそれを許してくれた。この頃であろうか、宝塚の近くの清荒神に住んでいた笹田和子を訪ね、声楽家になれるかどうかの助言を乞うたこともある。
1949年、旧制中学校を卒業していた彼は当時三年制の大阪学校(現在の大阪音楽大学)に入学し、すぐに附属高校二学年に編入された。砂川稔の音楽人生のスタートである。三年次には学校から四国に演奏旅行を行い、この時、朝比奈隆の指揮で「天地創造」の一節を独唱している。非公式ながら、これを彼のソリストとしてのデビューと見ることができよう。
1951年、大阪音校を卒業した彼は、さらなる修行のために上京し、国立音楽大学に入った。三年次までは関種子に、四年次にはネトケ・レーヴェに師事している。三年生の時、学生が主体となり「カヴァレリア・ルスティカーナ」が上演されることになり、トゥリッドゥを歌った。アルフィオを清水義人が歌ったこともあり、演出はその母堂で浅草オペラの大スター・清水静子が引き受けてくれた。この公演が、砂川稔の非公式なオペラ・デビューとなった。

1955年、国立音大を卒業した彼は、藤原義江のオーディションを受け、藤原歌劇団に入り、団員としてさまざまな公演に参加していくことになる。彼のオペラ歌手としての公式デビューは、その年の暮れに行われた、約一ヶ月の労音公演「カルメン」におけるレメンダート役である。主役は北沢栄、永田弦次朗で、指揮は近藤秀麿だった。翌年の4月、マスネ作曲「舞姫タイース」の日本初演で、初めて大役ニシアスをまかされた。砂原美智子がタイースを、石津憲一がアタナエルを歌った。この年の8月から12月まで、藤原歌劇団は第三次渡米公演を行い、彼もこれに加わっている。 1959年からは、東洋音楽学校(現在の東京音楽大学)付属音楽高校及び同学専攻科の教鞭をとりはじめるが、その傍ら演奏活動は続けられる。その年11月の、藤原歌劇団「青年グループ」による「ウィンザーの陽気な女房たち」(日本初演)でじゃフェントンを歌っている。やがて、彼は藤原家劇団を辞め、二期会に移ることになる。この折、藤原義江は、「君にレンスキー(チャイコフスキー作曲「エフゲニー・オネーギン」)を歌ってもらおうと思っていたのに・・・」ち残念がったという(筆者も、レンスキーは砂川稔にとってはまり役だったかも知れぬと思う)。二期会移籍後、1960年10月の「ホフマン物語」主役、1961年4月の「椿姫」アルフレード役(労音)というように、この頃(三十歳)の彼はリリック・テノールとしての地歩を着実に斯界に築いていったように見える。
しかし、やがて三十二歳をむかえようとしていた彼は、その基盤を敢然と捨て、ヨーロッパをめざす。すぐれた批評家で、砂川稔の芸術を知悉していた木村重雄は、「・・・・しかし、はたして彼の本意が、こうしたイタリアやフランス・オペラの華やかな主役として脚光を浴びることを求めていたかどうか。それは、すこぶる疑わしい。勿論、この国でも成功するためにはオペラを選び、主役で認められねばならないし、それはこの段階で一応果たしたとみてさしつかえない。しかし彼は、あえて日本での活動をふりすてて、さらに声楽家としての基盤を固めるべくウィーンに渡り、国立音楽院で学ぶこととなる。1962年秋のことである。・・・・」と書いている。ウィーンではエリザベート・ラドーとアントン・デルモータに学んだ。ことに名テノール・デルモータの端正な歌唱様式は彼にとって大きな規範となった。
1964年、ウィーン音楽祭におけるベートーヴェンの「ミサ・ソレムニス」(指揮/R・クナール)、またウィーン・バロックアンサンブル定期におけるバッハの「クリスマス・オラトリオ」(指揮/T・グシュルバウアー)のソロは、彼の力量がウィーンでも認められた証左であった。この他にも、数々のオーケストラや合唱団と共演して、オラトリオのソリストとして活動している。北独デトモルトに赴き、ギュンター・ヴァイセンボルンのもとで半年間、堅固なリート演奏法を学んだことや、ブルガリア国立オペラ研究員として、当時まだ情報の少なかった彼地で見聞を広めることができたのは貴重な体験だった。

1967年4月、帰国する。この後、幾度かの渡欧はあるが、彼の活動は日本国内に集約されていく。1969年1月の「ラインの黄金」のミーメ、6月の「こうもり」のアルフレード、そして、11月の「魔笛」のタミーノと、様式や性格の異なる諸役を見事に演じた。大木正興は砂川のタミーノについて、「今度の上演は音楽的にたいへん立派なものであった。(中略)タミーノの砂川稔は声も歌い方も今後大いに楽しめそうだ。『絵姿のアリア』など叙情味も格調も十分。」と評している。1970年9月の「フィデリオ」ではヤキーノを歌い、12月にはシュミット・イッセルシュセットの指揮でベートーヴェンの「ミサ・ソレムニーラー」のソロを、東敦子や荒道子、大橋国一と共に担っている。またマーラーの「嘆きの歌」のソロもこの年である。オペラではともかく、トラトリオの分野では長い間、官学出(上野系)がソロを独占してきた感があるが、砂川稔は初めてそこに進出した私学系のテノールであるということは特筆できる。
1968年から開始された東京室内歌劇場の活動には、その第一回公演から参加し、ガルッピの「田舎の知恵者」、ブゾーニの「アルレッキーノ」、ヒンデミットの「往きと復り」、エックの「検察官」などの作品において、知的で個性的な役作りを行っている。本来のリリック・テノールに、性格派テノール(Charaktertenor)の要素が加わってきた頃と言える。1975年のヴォルフ協会による「コレヒドール」日本初演(演奏会形式)における主役もまた、この彼の特性に適ったものであった。
1974年5月17日に行った初めてのリサイタルは、声楽家としての彼の経験と個性が結実したものであった。レーガーとブラームスの歌曲とヤナーチェクの「消え失せた男の日記」全曲(日本人として初演)を組み合わせたきわめて特異なプログラミングは、まさに彼独自の世界を打ち出していた。
1981年11月の二期会「カーチャ・ガバノヴァ」と12月の非常な好評をもって迎えられたリサイタル(ベートーヴェン、ブラームス、シュトラウスの歌曲)をもって、彼の声楽家としての歩みは途切れる。
この後、1995年に国立音大教授を退くまで、彼は後進の指導に一意専心する。しかし、退任後の彼が再び芸術家魂を燃やし、今度は指揮活動に入ったことはひとつの驚異であった。大患との闘いの中で、生きることを、音楽にたずさわることの意味を見つめ直したとも言える。古今の大作オラトリオの演奏に意欲を注ぎ、最近では、2009年にブラームスの「ドイツ・レクイエム」を、2010年にはドヴォルザークの「レクイエム」に取り組んだ。彼はその姿勢によって、音楽と共に歩いた六十年間に培われた彼の世界観を伝えようとしていると思える。八十歳の青年、その気概や高しと讃えたい。